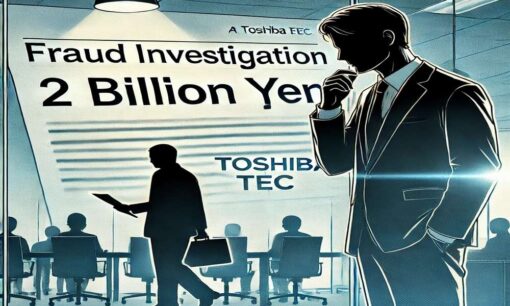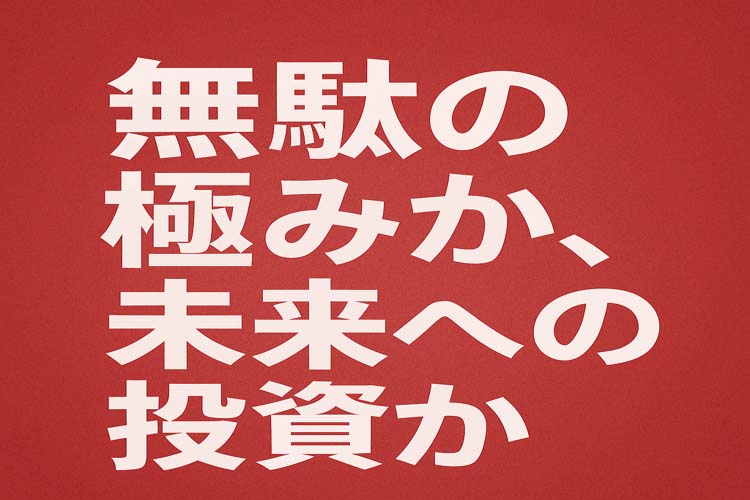
こども家庭庁が5月21日に発表した、性や妊娠に関する正しい知識を若年層に広める「プレコンセプションケア」の初の5カ年計画案が、SNS上で波紋を広げている。啓発人材「プレコンサポーター」を5万人養成するという内容に対し、「こんなことに人員や予算を割くのは無駄ではないか」とする声や、「子どもを産んだ人に1000万円配った方がよほど少子化対策になる」といった本音が続出している。
啓発に5万人、5年間 “スケール感”に違和感
こども家庭庁が今回打ち出した施策は、避妊や不妊治療、婦人科がん、無理なダイエット、高齢出産に関するリスクなどをテーマに、若年層の健康意識を高めるための啓発活動を推進するもの。その担い手として、企業や自治体、学校などで講習を行う「プレコンサポーター」を5万人規模で養成するという。
しかしX(旧Twitter)上では、「研修にいくらかけるつもりだ」「啓発という名の自己満足政策」「まず保育士の待遇を上げてから言え」といった否定的な声が相次いだ。
「それより現金配れ」 SNSに噴き出すリアルな声
中でも多かったのは、「回りくどい施策を打つくらいなら、子どもを産んだ人に現金を渡せ」という意見だ。
「子ども1人産んだら1000万円支給すれば、出生率は一気に上がる」「カネを使う場所がズレてる」「まず生活の基盤が不安定だから、啓発されても産む気にならない」といった投稿が続き、制度の意図や背景よりも、即効性を求める現実的な感覚が目立った。
また、「こども家庭庁に予算つけるくらいなら、子育て世帯への現物支給を厚くしてくれ」という声も多く、制度そのものではなく、国の資源配分の方向性への不満もにじむ。
世界は“知識の土台”を重視 日本はようやく第一歩
とはいえ、プレコンセプションケアは国際的にはすでに常識となりつつある。米国ではCDC(疾病予防管理センター)が妊娠前からの健康管理を公衆衛生の柱に位置付け、包括的な性教育を実施。フィンランド、オランダなどの北欧諸国では、義務教育でリプロダクティブ・ヘルスの知識が必須項目となっている。
日本では、性や生殖に関する教育の機会は極端に少なく、無知がゆえのリスクが表面化しにくい土壌がある。若年層の痩身化、不妊の増加、婦人科疾患の放置といった問題は、知識の欠如と深く結びついていると指摘されてきた。
問われるのは「情報」と「支援」、どちらが先か
計画では、プレコンセプションケアの認知度を30代以下で80%まで高めることを目標に掲げ、専門相談可能な医療機関も5年間で200カ所以上に増設する方針だ。プレコンサポーターは保健師や養護教諭、人事担当者などを想定しており、地域に根ざした情報発信の起点とする狙いがある。
だが、SNSでの反応は明確だった。多くの人々が「啓発よりまず実利」「講習より現金」「研修より保育所」と感じていることが浮かび上がった。知識の普及も確かに重要だが、それ以前に求められる「安心して子を産み育てられる環境整備」が、なお不十分であることの裏返しともいえる。